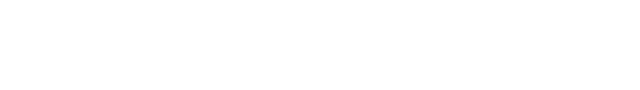各検査項目の詳細
このページでは、健康診断の主要な検査項目について、それぞれの数値が何を意味し、どんな病気の可能性を示唆するのかを分かりやすく解説します。
健診結果の基本
健診結果表には、各検査項目の数値の隣に「基準値」や「基準範囲」が記載されています。この基準値から外れている場合、「異常値」とされます。しかし、異常値が出たからといって、すぐに病気と診断されるわけではありません。体調や生活習慣、測定時の状況などによって一時的に変動することもあります。
大切なのは、個々の数値だけでなく、全体のバランスや過去のデータとの比較、そして何よりも医師による総合的な判断です。
各検査項目の見方
血圧
血圧は、心臓が血液を全身に送り出す際に血管にかかる圧力のことです。心臓が収縮して血液を送り出すときの「最高血圧(収縮期血圧)」と、心臓が拡張して血液を取り込むときの「最低血圧(拡張期血圧)」の二つの数値で評価されます。一般的な正常値は、最高血圧が120mmHg未満、最低血圧が80mmHg未満とされています。
この数値が高値だった場合は高血圧と診断されます。高血圧は自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行していることが多く、「サイレントキラー」とも呼ばれます。放置すると血管に常に高い圧力がかかることで動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中、さらには腎臓病などの重篤な合併症を引き起こすリスクが格段に高まります。一方、低値だった場合は低血圧と呼ばれ、立ちくらみやめまい、全身のだるさ、倦怠感といった症状が見られることがあります。
LDLコレステロール(悪玉コレステロール)
LDLコレステロールは、肝臓で合成されたコレステロールを全身の細胞に運ぶ役割を担うリポタンパク質で、一般に「悪玉コレステロール」と呼ばれています。この数値が高すぎると、血管の内壁にコレステロールが過剰に蓄積され、動脈硬化を促進してしまいます。一般的な正常値は120mg/dL未満とされます。この数値が高値だった場合は脂質異常症の一種と診断され、動脈硬化が進行しやすくなることで、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞といった重篤な心血管疾患のリスクが著しく高まります。
HDLコレステロール(善玉コレステロール)
HDLコレステロールは、全身の細胞や血管壁にたまった余分なコレステロールを回収し、肝臓へと戻す役割を担うリポタンパク質で、「善玉コレステロール」と呼ばれます。動脈硬化の進行を抑制する働きがあるため、動脈硬化を予防するためにはこの値が高いことが望ましいとされています。一般的な正常値は40mg/dL以上です。この数値が低値だった場合は脂質異常症の一種と診断され、LDLコレステロールが高値の場合と同様に、動脈硬化のリスクが高まることが指摘されています。
トリグリセライド(中性脂肪)
トリグリセライドは、体内でエネルギー源として貯蔵される脂肪の一種で、食事から摂取した脂肪や糖質から肝臓で合成されます。主に皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられますが、血液中の数値が増えすぎると健康に悪影響を及ぼします。一般的な正常値は30~149mg/dLとされます。この数値が高値だった場合は脂質異常症の一種と診断され、肥満や糖尿病のリスクを高めるだけでなく、LDLコレステロールの異常と相まって動脈硬化を進行させる原因となることがあります。
血糖(GLU)
血糖は血液中のブドウ糖の濃度を示す数値です。ブドウ糖は体の主要なエネルギー源であり、血糖値は食事によって変動するため、健康診断では通常、空腹時(検査前10時間以上食事をしていない状態)に測定されます。一般的な正常値は空腹時100mg/dL未満とされます。この数値が高値だった場合は、検査時点での血糖値が高い状態であり、糖尿病の可能性が強く考えられます。高血糖が続くと、のどの渇き、多尿、体重減少などの症状が現れることもあります。一方、低値だった場合は低血糖と呼ばれ、強い空腹感、動悸、冷や汗、手の震え、倦怠感といった症状が現れることがあります。
HbA1c(ヘモグロビンA1c)
HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)は、過去1〜2ヶ月間の血糖値の平均を反映する非常に重要な指標です。赤血球の中にあるヘモグロビンというタンパク質が、血液中のブドウ糖と結合した割合を示します。通常の血糖値が採血時の状態を反映するのに対し、HbA1cは過去の血糖コントロールの状態を把握できるため、糖尿病の診断や治療効果の評価に用いられます。一般的な正常値は5.6%未満とされます。この数値が高値だった場合は、過去1~2ヶ月にわたって血糖値が高い状態が続いていたことを示しており、糖尿病の可能性や、すでに糖尿病と診断されている方の血糖コントロールが不良であることを意味します。
AST(GOT)
AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、GOTとも呼ばれる)は、肝臓の細胞のほか、心臓や筋肉、腎臓などにも多く存在する酵素です。これらの細胞が障害を受けて壊れると、血液中に流れ出し、数値が上昇します。一般的な正常値は30U/L以下とされます。この数値が高値だった場合は、肝機能障害(ウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、脂肪肝など)や心筋梗塞、筋炎などの筋肉の病気などの可能性が考えられます。
ALT(GPT)
ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ、GPTとも呼ばれる)は、主に肝臓の細胞に多く存在する酵素です。ASTと同様に、肝臓の細胞が壊れた際に血液中に流れ出し、数値が上昇します。一般的な正常値は30U/L以下とされます。この数値が高値だった場合は、脂肪肝や肝炎など、肝機能障害の可能性が強く示唆されます。ALTはASTと比較して、より肝臓の異常に特異性が高いと言われています。
γ-GTP
γ-GTP(ガンマ・グルタミルトランスペプチダーゼ)は、肝臓や胆道に多く存在する酵素です。肝臓や胆道の異常で数値が上昇するほか、アルコールの過剰摂取によっても数値が上昇しやすいことで知られています。薬剤の影響で上昇することもあります。一般的な正常値は男性50U/L以下、女性30U/L以下とされます。この数値が高値だった場合は、肝機能障害(脂肪肝、肝炎など)や胆道系の病気(胆管炎、胆石など)、アルコール性肝障害などが考えられます。
ALP
ALP(アルカリホスファターゼ)は、肝臓や胆道、骨などに多く存在する酵素です。一般的な正常値は100~350U/Lとされます。この数値が高値だった場合は、胆汁の流れが滞る肝胆道系の異常(胆石、胆管炎など)や、骨の病気(骨折、骨粗しょう症、骨腫瘍など)、または一部の腫瘍などが考えられます。小児期や妊娠中には生理的に高値を示すこともあります。
LDH
LDH(乳酸脱水素酵素)は、全身の様々な臓器に存在する酵素です。細胞が壊れると血液中に流れ出し、数値が上昇します。一般的な正常値は120~245U/Lとされます。この数値が高値だった場合は、肝臓、心臓、腎臓、肺、筋肉、あるいは血液疾患(溶血性貧血など)など、全身の様々な臓器に障害が起きている可能性が考えられます。
尿糖
尿糖検査では、尿中に糖が含まれているかどうかを調べます。通常、健康な人の尿には糖は含まれていないため、陰性(-)が正常です。この検査で陽性だった場合は、血糖値が高い状態を示唆し、糖尿病の可能性が考えられます。ただし、一時的な高血糖や、腎臓の機能によっては血糖値が正常でも尿糖が出ることがあるため、陽性の場合は精密検査が必要となります。
尿蛋白
尿蛋白検査では、尿中にタンパク質が含まれているかどうかを調べます。通常、健康な人の尿にはタンパク質はほとんど含まれないため、陰性(-)が正常です。この検査で陽性だった場合は、腎臓に何らかの異常がある可能性があり、慢性腎臓病の早期発見に繋がる重要なサインとなります。激しい運動後や発熱時、起立性蛋白尿と呼ばれる一時的な状態でも陽性になることがありますが、持続する場合は精密検査が必要です。
尿潜血
尿潜血検査では、尿中に目に見えないごくわずかな血液が混じっているかどうかを調べます。通常は陰性(-)が正常です。この検査で陽性だった場合は、腎臓や尿路系の疾患(尿路結石、膀胱炎、腎炎、腎臓や膀胱の腫瘍など)の可能性を示唆します。女性の場合、生理中に検査すると陽性になることがあるため注意が必要です。
尿酸(UA)
尿酸は、体内でプリン体という物質が分解される際に作られる老廃物の一種です。通常は尿として体外に排出されます。一般的な正常値は男性3.0~7.0mg/dL、女性2.5~6.0mg/dLとされます。この数値が高値だった場合は高尿酸血症と呼ばれ、尿酸が体内で過剰に作られたり、うまく排出されなかったりしている状態です。高尿酸血症は、激しい関節の痛みを伴う痛風関節炎を引き起こすほか、腎臓病や動脈硬化のリスクを高めることがあります。
クレアチニン
クレアチニンは、筋肉の代謝によって生じる老廃物で、主に腎臓から尿として排出されます。腎臓のろ過機能を示す重要な指標の一つです。一般的な正常値は男性0.6~1.1mg/dL、女性0.4~0.8mg/dLとされます。この数値が高値だった場合は腎機能低下の可能性があり、腎臓が老廃物を十分に排泄できていない状態を示します。クレアチニンの高値は、**慢性腎臓病(CKD)**の診断に繋がる可能性があります。
eGFR(推算糸球体ろ過量)
eGFR(estimated Glomerular Filtration Rate:推算糸球体ろ過量)は、腎臓が血液をろ過する能力を示す指標です。クレアチニンの値と年齢、性別から推算され、腎臓の働きをより正確に評価するために用いられます。一般的な正常値は60mL/min/1.73m²以上とされます。この数値が低値だった場合は**慢性腎臓病(CKD)**の可能性があります。数値が低いほど腎機能が低下していることを示し、腎臓病の進行度を判断する上で非常に重要です。
赤血球数(RBC)/ ヘモグロビン(Hb)/ ヘマトクリット(Ht)
これらは血液中の赤血球に関する主要な項目です。
赤血球数(RBC)は血液中の赤血球の数を、ヘモグロビン(Hb)は赤血球に含まれる酸素を運ぶ赤い色素の量を、ヘマトクリット(Ht)は血液全体に占める赤血球の割合をそれぞれ示します。一般的な正常値はそれぞれ男女で異なります(RBC: 男性 420~570万/µL, 女性 370~520万/µL / Hb: 男性 13.5~17.0g/dL, 女性 11.5~15.0g/dL / Ht: 男性 40~50%, 女性 35~45%)。
これらの数値が低値だった場合は貧血の状態です。貧血になると、酸素を全身に十分に運べなくなり、立ちくらみ、息切れ、疲労感、動悸などの症状を引き起こすことがあります。一方、高値だった場合は多血症や、脱水状態、喫煙などが考えられます。多血症は血液の粘度を高め、血栓ができやすくなるリスクがあります。
白血球数(WBC)
白血球は、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物と戦う免疫細胞の数を調べます。一般的な正常値は3,500~9,000/µLです。
この数値が高値だった場合は、体内で細菌感染症や炎症が起きている可能性、ストレス、あるいは白血病などの血液の病気が考えられます。低値だった場合は、ウイルス感染症、薬剤の影響、免疫機能の低下、骨髄の異常などが原因として考えられ、感染症に対する抵抗力が低下している可能性があります。
血小板数(Plt)
血小板は、血液中に含まれる小さな細胞で、出血した際に集まって血を固め、止血する非常に重要な働きを担っています。傷口をふさぎ、かさぶたを作るのも血小板の働きによるものです。一般的な正常値は15万~35万/µLです。この数値が基準値よりも高値だった場合は、体内で炎症や感染症が起きている可能性、あるいは鉄欠乏性貧血や特定の血液疾患などが考えられます。一方、低値だった場合には、出血が止まりにくい、鼻血が出やすい、または体に覚えのないあざができやすいといった症状が見られることがあります。これは、免疫疾患、肝疾患、骨髄の異常など、様々な原因が考えられます。
異常値が見つかったら、まずご相談ください
健診結果で気になる項目や異常値があった場合は、ご自身の判断だけで不安を抱え込まず、必ず医療機関にご相談ください。当院では、各検査項目の意味を分かりやすくご説明し、必要に応じて精密検査や治療計画をご提案いたします。
特に、高血圧、糖尿病、脂質異常症、腎臓病といった生活習慣病は、初期には自覚症状が少ないまま進行し、放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があります。当院はこれらの疾患の専門医が在籍しており、きめ細やかな生活指導から専門的な治療まで、患者様お一人おひとりに合わせたサポートを提供いたします。女性医師による診察も可能ですので、安心してご来院ください。