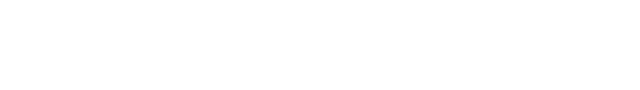慢性腎臓病を有する高齢者におけるタンパク質摂取と予後
慢性腎臓病(慢性腎不全、CKD)の食事指導はとても重要な問題で、患者さんの関心が一番高いところでもあります。主に外来で言われるのが(患者さんの状況にもよりますが)、①塩分制限、②蛋白制限、③果物・生野菜摂取の制限、といったところかと思います。塩分制限に関しては、割とコンセンサスが得られているという認識ですが、有名な蛋白制限に関しては、学術集会でも議論のネタになっていることが多く、重要な話題です。これは、蛋白摂取により老廃物が蓄積して腎臓に負担をかけるのではないかとか、尿毒症を引き起こすのではないか、という懸念がある一方で、蛋白制限をすると筋力が弱って、ただでさえCKD患者さんは高齢者が多いのに、その虚弱性を悪化させるのではないかという懸念もあって議論になっているというのがあります。
そこで、今回は、スペインからの報告で、CKD患者さんの蛋白摂取量と予後をみた報告があったので読んでみました。
重要性: 慢性腎臓病(CKD)を抱える高齢者において、高タンパク質摂取を避けることが腎機能の低下リスクを減らす可能性があるが、それが生存に対して最適でないかどうかはよく分かっていない。
目的: 軽度から中等度のCKDを有する高齢者における総タンパク質摂取量、動物性タンパク質摂取量、および植物性タンパク質摂取量と、全死亡率との関連を推定し、その結果をCKDを持たない高齢者と比較すること。
デザイン、設定、参加者: 本研究は、3つのコホート(スペインにおける高齢者の心血管健康、栄養および虚弱に関する研究1および2、スウェーデンにおけるKungsholmen地域の老年期ケアに関する全国的研究)のデータを使用した。これらのコホートは、60歳以上の地域社会に居住する成人を対象としている。参加者は2001年3月から2017年6月にかけて募集され、2021年12月から2024年1月までの期間に死亡に関する追跡調査が行われた。食事や死亡に関する情報がない者、CKDステージ4または5の者、腎代替療法を受けている者、および腎移植受容者は除外された。データは2023年6月から2024年2月にかけて初回分析され、2024年5月に再分析された。
曝露: 検証済みの食事歴および食物摂取頻度調査を使用して推定された累積タンパク質摂取量。
主要な結果および測定: 研究の主な結果は、10年間の全死亡率であり、国の死亡登録を用いて確認された。慢性腎臓病は推定糸球体濾過率、尿中アルブミン排泄量、および医療記録からの診断に基づいて確認された。
結果: 研究サンプルは8543名の参加者と14,399件の観察結果で構成された。CKDステージ1から3の4789件の観察結果のうち、2726件(56.9%)が女性に該当し、平均年齢(標準偏差)は78.0(7.2)歳であった。追跡期間中に1468件の死亡が記録された。CKDを有する参加者において、総タンパク質摂取量が多いほど死亡率が低くなったことが示された。1.00対0.80g/kg/日では調整済みハザード比(HR)は0.88(95%信頼区間[CI], 0.79-0.98)、1.20対0.80g/kg/日では0.79(95% CI, 0.66-0.95)、1.40対0.80g/kg/日では0.73(95% CI, 0.57-0.92)であった。植物性および動物性タンパク質の摂取量と死亡率との関連も同様であった(それぞれHR, 0.80 [95% CI, 0.65-0.98]および0.88 [95% CI, 0.81-0.95]、0.20g/kg/日の増加につき)。75歳未満の参加者と75歳以上の参加者における総タンパク質摂取量の増加に伴う死亡率のハザード比はそれぞれ0.94(95% CI, 0.85-1.04)および0.91(95% CI, 0.85-0.98)であった。しかし、CKDを有しない参加者におけるハザード比は、CKDを有する参加者よりも低かった(それぞれHR, 0.85 [95% CI, 0.79-0.92]および0.92 [95% CI, 0.86-0.98]、0.20g/kg/日ごとの増加につき; 相互作用に対するP = .02)。
結論および関連性: この複数のコホートを対象とした高齢者の研究において、総タンパク質、動物性タンパク質、植物性タンパク質の摂取量が多いほど、CKDを有する参加者における死亡率が低下することが示された。CKDを有しない者の方が関連性が強かったことから、軽度または中等度のCKDを有する高齢者においても、タンパク質の利点がデメリットを上回る可能性がある。
◾️コメント
この報告では、蛋白摂取量が多いほど死亡率が下がることが報告されました。個人的には、外来で蛋白制限するのは、透析に至る直前の時期のみです。この時期は、尿毒症を惹起して透析導入が早めるのを懸念してそのようにしてます。なのでCKD患者さんであっても、よく食べて(いくつか気をつける点はありますが)、よく運動して、適切に感染性疾患を予防する(病院で勤務医をしていた時の実感としては、感染症による入院は筋肉量低下に一気に拍車をかけます)というのがやはり重要なのかなと思ってます。
もし筋肉量が気になる方は、InBodyで1分間で測定できるので、是非ご活用ください。
愛知県名古屋市西区
リウゲ内科小田井クリニック
副院長 龍華章裕 (総合内科専門医、日本腎臓学会専門医、日本透析医学会専門医)