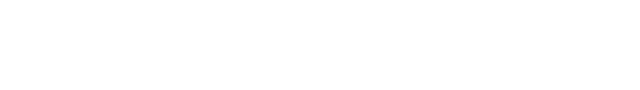脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症(高脂血症)とは
脂質異常症は、血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂質の値が基準範囲から外れる状態を指します。以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、脂質には良い働きをするもの(HDLコレステロール)もあるため、現在は脂質異常症という名称が使われています。自覚症状がほとんどないため、健康診断などで指摘されて初めて気づくことが多い病気です。しかし、放置すると動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めてしまいます。
こんな方は脂質異常症に要注意
以下に当てはまる方は、脂質異常症のリスクが高いと考えられます。一つでも心当たりのある方は、一度当院にご相談ください。
- 健康診断でコレステロールや中性脂肪の数値が高いと指摘された方
- 肥満気味、またはメタボリックシンドロームと診断された方
- 高血圧、糖尿病を指摘されている方
- 喫煙習慣のある方
- 運動不足の方
- 食生活が不規則で、脂っこいものや甘いものをよく食べる方
脂質異常症の原因
脂質異常症の原因は、大きく分けて原発性(体質によるもの)と続発性(他の病気や生活習慣によるもの)があります。
原発性脂質異常症
原発性脂質異常症は、遺伝的な要因や体質によって、脂質代謝に関わる酵素や受容体の働きに異常がある場合に起こります。家族性高コレステロール血症などが代表的です。
続発性脂質異常症
続発性脂質異常症は、生活習慣の乱れや他の病気が原因で起こる脂質異常症です。これらの要因は改善が可能なため、生活習慣の見直しや原因となる病気の治療が重要になります。
食生活では、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸、コレステロールを多く含む食品の過剰摂取は脂質バランスを崩します。また、糖質の摂りすぎは中性脂肪を増やし、食物繊維やビタミン、ミネラルの不足も脂質代謝に悪影響を及ぼします。
運動不足はエネルギー消費を低下させ、脂質代謝を滞らせます。喫煙は血管を傷つけLDLコレステロールの酸化を促進し、HDLコレステロールを低下させます。過剰な飲酒は肝臓での中性脂肪合成を促進します。
肥満、特に内臓脂肪の蓄積は、インスリン抵抗性を高め、脂質異常症を引き起こしやすくします。さらに、糖尿病や甲状腺機能低下症、慢性腎臓病などの病気や、一部の薬剤(副腎皮質ステロイド、経口避妊薬など)も脂質の値に影響を与えることがあります。
脂質異常症の判断基準
脂質異常症は、血液検査によって診断されます。一般的には、総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪の4つの項目が測定されます。これらの数値を総合的に評価し、治療方針が決定されます。
|
LDLコレステロール |
境界域高LDLコレステロール血症 |
120~139 mg/dL |
|
高LDLコレステロール血症 |
140 mg/dL以上 |
|
|
HDLコレステロール |
低HDLコレステロール血症 |
40 mg/dL未満 |
|
中性脂肪 |
高トリグリセリド血症 |
150 mg/dL以上 |
健康診断で脂質の値に異常が見られた場合は、放置せずに必ず医療機関を受診し、医師の診断と指導を受けるようにしてください。
脂質異常症の症状
脂質異常症は、基本的に自覚症状がありません。そのため「サイレントキラー(静かなる殺人者)」とも呼ばれています。しかし、病状が進行し、動脈硬化が著しくなると、以下のような症状が現れることがあります。
- 胸の痛みや圧迫感
- 手足のしびれ、痛み
- めまい、頭痛、ろれつが回らないなどの脳の症状
これらの症状が現れた時には、すでに病気が進行している可能性が高いです。自覚症状がなくても、定期的な健康診断で早期発見・早期治療を行うことが非常に重要です。
脂質異常症の治療
脂質異常症の治療は、生活習慣の改善を基本とし、必要に応じて薬物療法を併用します。治療の目標は、血液中の脂質値を適切な範囲に保ち、動脈硬化の進行を抑制し、心血管疾患の発症リスクを減らすことです。
生活習慣の改善
食事療法
脂質異常症の治療において、土台となるのは生活習慣の改善です。食事療法では、特に脂肪の摂取を意識的に控えましょう。具体的には、肉の脂身、バター、乳製品などに多く含まれる飽和脂肪酸や、マーガリン、ショートニング、加工食品などに含まれるトランス脂肪酸を避けることが大切です。また、卵黄、レバー、魚卵などのコレステロールを多く含む食品の摂取も控えめにするように心がけましょう。その一方で、野菜、果物、きのこ類、海藻類、豆類などに豊富な食物繊維は、コレステロールの吸収を抑える働きがあるため、積極的に摂り入れることが推奨されます。さらに、青魚に多く含まれるEPAやDHAといった栄養素は、中性脂肪を減らし、血液をサラサラにする効果が期待できます。日々の食事においては、これらの点に注意し、栄養バランスの取れた食事を心がけ、適正な体重を維持することが重要です。アルコールの過剰な摂取は中性脂肪を上昇させる原因となるため、適量を守るようにしましょう。
運動療法
運動療法も生活習慣改善の重要な柱の一つです。ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動は、中性脂肪を減らし、HDLコレステロールを増やす効果が期待できます。目安としては、1日に30分以上、週に3回以上行うことが推奨されます。加えて、筋肉量を増やす筋力トレーニングは、基礎代謝を向上させ、脂肪燃焼を促進する効果があります。運動を行う際には、自己判断ではなく、医師に相談し、無理のない範囲で継続していくことが大切です。
喫煙は脂質代謝を悪化させ、動脈硬化を促進する最大の要因の一つです。脂質異常症の治療においては、禁煙が最も重要な取り組みと言えるでしょう。
薬物療法
生活習慣の改善だけでは脂質の数値が改善しない場合や、動脈硬化のリスクが高いと判断される場合には、薬物療法を検討します。患者様の状態やリスク因子に合わせて、以下の薬が処方されます。
- スタチン
LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を強力に下げる薬です。肝臓でのコレステロール合成を抑えることで作用します。 - フィブラート
主に中性脂肪を下げる薬です。肝臓での中性脂肪の合成を抑えたり、中性脂肪を分解する酵素の働きを高めたりすることで作用します。 - コレステロール吸収阻害薬
小腸でのコレステロール吸収を抑える薬です。食事から摂取されたコレステロールの吸収を阻害することで、血中のコレステロール値を下げます。
これらの薬剤は、患者さんの脂質値やその他の健康状態を考慮し、医師が慎重に選択します。自己判断で薬の服用を中止したり、量を変更したりすることは危険ですので、必ず医師の指示に従って正しく服用することが重要です。
当院での脂質異常症治療
名古屋市西区に位置するリウゲ内科小田井クリニックは、開業40年以上の歴史を持ち、地域に根差した医療を提供しています。当院には糖尿病専門医と腎臓専門医が在籍しており、脂質異常症が引き起こす合併症のリスクも考慮した総合的な診療が可能です。
患者さん一人ひとりのライフスタイルや状態に合わせたオーダーメイドの治療計画を立案しています。看護師や管理栄養士が在籍しており、食事内容や運動習慣の見直しについて、実践的で継続しやすい具体的なアドバイスを提供しています。生活習慣の改善だけでは脂質の数値が改善しない場合や、動脈硬化のリスクが高いと判断される場合には、患者さんの状態に合った適切な薬物療法を提案し、副作用や効果についても丁寧に説明します。
定期的な検査で効果を確認しながら、きめ細やかなサポートを継続することで、患者さんが安心して治療に取り組めるよう努めています。脂質異常症は自覚症状がなくても放置すると怖い病気です。少しでも気になることや不安なことがあれば、お気軽に当院にご相談ください。長年の経験と専門知識を持つ医師と、充実したサポート体制で、皆様の健康を支えてまいります。
文責:リウゲ内科小田井クリニック 副院長 龍華章裕