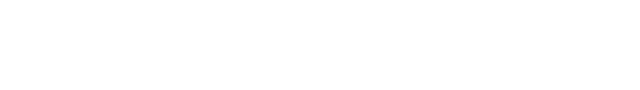高血圧
高血圧とは
高血圧とは、血管にかかる圧力(血圧)が慢性的に高い状態が続くことを指します。血圧は心臓が血液を全身に送り出す際に発生する圧力で、収縮期血圧(最高血圧)と拡張期血圧(最低血圧)の2つの数値で表されます。
一般的に、診察室での血圧が140/90mmHg以上、家庭での血圧が135/85mmHg以上の状態が継続する場合に高血圧と診断されます。高血圧は自覚症状がほとんどないため「サイレントキラー(沈黙の疾患)」とも呼ばれ、気づかないうちに血管や臓器に大きな負担をかけていることがあります。
こんな方は高血圧に要注意
以下のような方は、高血圧になるリスクが高いと考えられています。ご自身に当てはまる項目がないか確認してみましょう。
- 健康診断で血圧が高いと指摘された方
- ご家族に高血圧の方がいる方
- 喫煙習慣のある方
- 飲酒量が多い方
- 運動不足の方
- 肥満傾向の方
- ストレスが多い方
- 塩分の多い食事を好む方
高血圧の原因
高血圧の多くは、単一の原因によるものではなく、様々な要因が複雑に影響し合って発症します。高血圧患者さんの約9割を占めるのは本態性高血圧、または一次性高血圧と呼ばれるもので、明確な原因は特定されていません。しかし、前述の「こんな方は高血圧に要注意」で挙げたような遺伝的な体質や、日々の生活習慣の積み重ねが深く関わっていると考えられています。
一方、高血圧患者さんの約1割は二次性高血圧に該当します。これは、他の病気、例えば腎臓病や内分泌系の病気、血管の異常、あるいは睡眠時無呼吸症候群などが原因で引き起こされるものです。また、特定の薬剤の使用も二次性高血圧の原因となることがあります。二次性高血圧の場合、その原因となっている病気を適切に治療することで、高血圧の改善が見込める可能性があります。
高血圧のリスク・合併症
高血圧が長期間にわたって続くと、血管には絶えず負担がかかり、その影響は全身の様々な臓器に及んでしまいます。特に注意が必要なのが心血管疾患です。心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送ることができなくなる心不全や、心臓に血液を送る血管である冠動脈が詰まったり狭くなったりすることで心臓の筋肉が酸素不足に陥る心筋梗塞・狭心症などが挙げられます。また、脳の血管が詰まる脳梗塞や破れる脳出血、くも膜下出血といった脳卒中は、脳の機能に深刻な障害をもたらし、高血圧はこれらの病気における最大の危険因子の一つとされています。
さらに、腎臓の血管も高血圧によって硬化し、腎機能が徐々に低下していく慢性腎臓病も重要な合併症です。その他にも、血管の壁が厚く硬くなり弾力性を失う動脈硬化は高血圧によって進行し、眼の奥にある網膜の血管が損傷を受けて視力低下などを引き起こす眼底出血・網膜症、そして全身で最も太い血管である大動脈の壁が弱くなり瘤ができたり血管の壁が裂けたりする大動脈瘤・大動脈解離なども、高血圧が関与する深刻な合併症です。
これらの合併症は、日常生活の質を著しく低下させるだけでなく、時には命に関わることもあります。したがって、高血圧を早期に発見し、適切な管理を行うことが、健康な生活を送る上で非常に重要なのです。
高血圧の症状
高血圧は、初期にはほとんど自覚症状がないことが特徴です。そのため、健康診断などで指摘されるまで気づかないことが多いです。
しかし、血圧が非常に高くなると、以下のような症状が現れることがあります。
- 頭痛
- めまい
- 肩こり
- 動悸
- 息切れ
- 顔のほてり
- 耳鳴り
これらの症状は、高血圧以外にも様々な原因で起こりうるため、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。
高血圧の診断
高血圧の診断では、血圧測定が非常に重要になります。血圧測定には、医療機関で医師や看護師が測定する診察室血圧と、ご自宅で患者さんご自身が測定する家庭血圧の二種類があります。家庭血圧を毎日測定していただくことで、より日常に近い血圧の状態を把握でき、診察室での血圧だけでは見逃されがちな「白衣高血圧」や「仮面高血圧」の発見にもつながり、診断や治療計画に役立てることが可能です。
当院では、これらの血圧測定に加え、問診や身体診察、血液検査、尿検査、心電図検査などを総合的に判断し、患者様一人ひとりの状態に応じた最適な診断を行います。
高血圧の降圧目標
高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019ガイドライン)の降圧目標によれば、一般的な高血圧患者の目標血圧は以下の通りです。
| 診察室血圧 | 家庭血圧 | |
|---|---|---|
| 75才未満の成人 脳血管障害患者(両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし) 冠動脈疾患患者 慢性腎臓病患者(蛋白尿陽性) 糖尿病患者 抗血栓薬服薬中 |
130/80 | 125/75 |
| 75才以上の高齢者 脳血管障害患者(両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり、または未評価) 慢性腎臓病患者(蛋白尿陰性) |
140/90 | 135/85 |
高血圧の治療
高血圧の治療の基本は、生活習慣の改善と薬物療法です。患者さんの状態や合併症の有無などを考慮して、最適な治療法を決定します。
生活習慣の改善
食事療法
生活習慣の改善においては、まず食事療法が重要となります。具体的には、1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることが推奨されており、薄味に慣れる工夫や、香辛料や酸味を上手に活用した調理法を取り入れると良いでしょう。また、野菜、果物、海藻類などに豊富に含まれるカリウムは、体内の余分なナトリウムを排出し、血圧を下げる効果が期待できます。さらに、野菜、果物、きのこ類、豆類などに含まれる食物繊維は、便通を整えるだけでなく、コレステロールの吸収を抑制する働きもあります。日々の食事においては、栄養バランスの取れた食事を心がけ、適正な体重を維持することも大切です。
運動療法
運動療法も、高血圧の治療において重要な役割を果たします。ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を、1日に30分以上、週に3回以上行うことが推奨されています。ただし、運動を行う際には、必ず医師に相談し、無理のない範囲で継続することが大切です。
その他
禁煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるだけでなく、動脈硬化を促進するため、高血圧治療において非常に重要です。アルコールの過剰摂取も血圧を上昇させる可能性があるため、適量を守るようにしましょう。また、ストレスは血圧を上昇させる要因となるため、適度な休息や趣味の時間を持つなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。質の高い睡眠を確保することも、血圧の安定につながります。
薬物療法
これらの生活習慣の改善だけでは血圧が十分に下がらない場合や、既に合併症がある場合には、薬物療法が行われます。
高血圧の治療薬
- 利尿薬
体内の余分な水分と塩分を尿として排出することで、血液の量を減らし、血圧を下げます。むくみやすい方や心臓に負担がかかっている方にも用いられます。 - β遮断薬
心臓の働きを抑え、心拍数を減らしたり、心臓から送り出す血液の量を減らしたりすることで、血圧を下げます。狭心症や不整脈を合併している方にもよく使用されます。 - ACE阻害薬
血圧を上げる原因となる物質(アンジオテンシンII)の生成を抑えることで、血管を広げ、血圧を下げます。特に、糖尿病性腎症や心不全を合併している場合に選択されることがあります。空咳(からぜき)が副作用として出ることがあります。 - ARB
血圧を上げる物質(アンジオテンシンII)が血管に作用するのを直接ブロックすることで、血管を広げ、血圧を下げます。ACE阻害薬で空咳の副作用が出やすい方にも使用されます。腎臓保護作用も期待されます。 - カルシウム拮抗薬
血管の細胞へのカルシウムの流入を抑えることで、血管を広げ、血圧を下げます。安定した降圧効果が期待でき、脳血管障害や心臓病の予防にも用いられます。頭痛やほてりなどの副作用が出ることがあります。
これらの薬剤は単独で用いられることもあれば、複数の薬剤を組み合わせて使用することで、より効果的に血圧をコントロールすることもあります。治療薬の選択や服用方法は、必ず医師の指示に従ってください。
当院での高血圧治療
名古屋市西区にあるリウゲ内科小田井クリニックでは、開業40年以上の経験に基づき、患者様一人ひとりに合わせた高血圧治療を提供しています。
当院には、糖尿病専門医と腎臓専門医が在籍しており、高血圧と密接に関わるこれらの合併症のリスクを早期に評価し、専門医ならではのきめ細やかなアプローチで包括的な高血圧管理を行います。また、管理栄養士が患者様一人ひとりの食生活に合わせた具体的な減塩方法やバランスの取れた食事のコツなど、実践しやすい栄養指導を提供し、健康的な生活習慣の確立をサポートします。
40年以上にわたり地域医療に貢献してきた「かかりつけ医」として、患者様との信頼関係を大切にし、定期的な診察を通じて安心して治療を続けられるようサポートいたします。
高血圧は、適切な管理によって健康寿命を延ばし、合併症のリスクを低減できる病気です。名古屋市西区で高血圧にお悩みの方、健康診断で血圧が高いと指摘された方は、ぜひ一度、リウゲ内科小田井クリニックにご相談ください。私たち専門医とスタッフが、皆様の健康を全力でサポートいたします。
文責:リウゲ内科小田井クリニック 副院長 龍華章裕